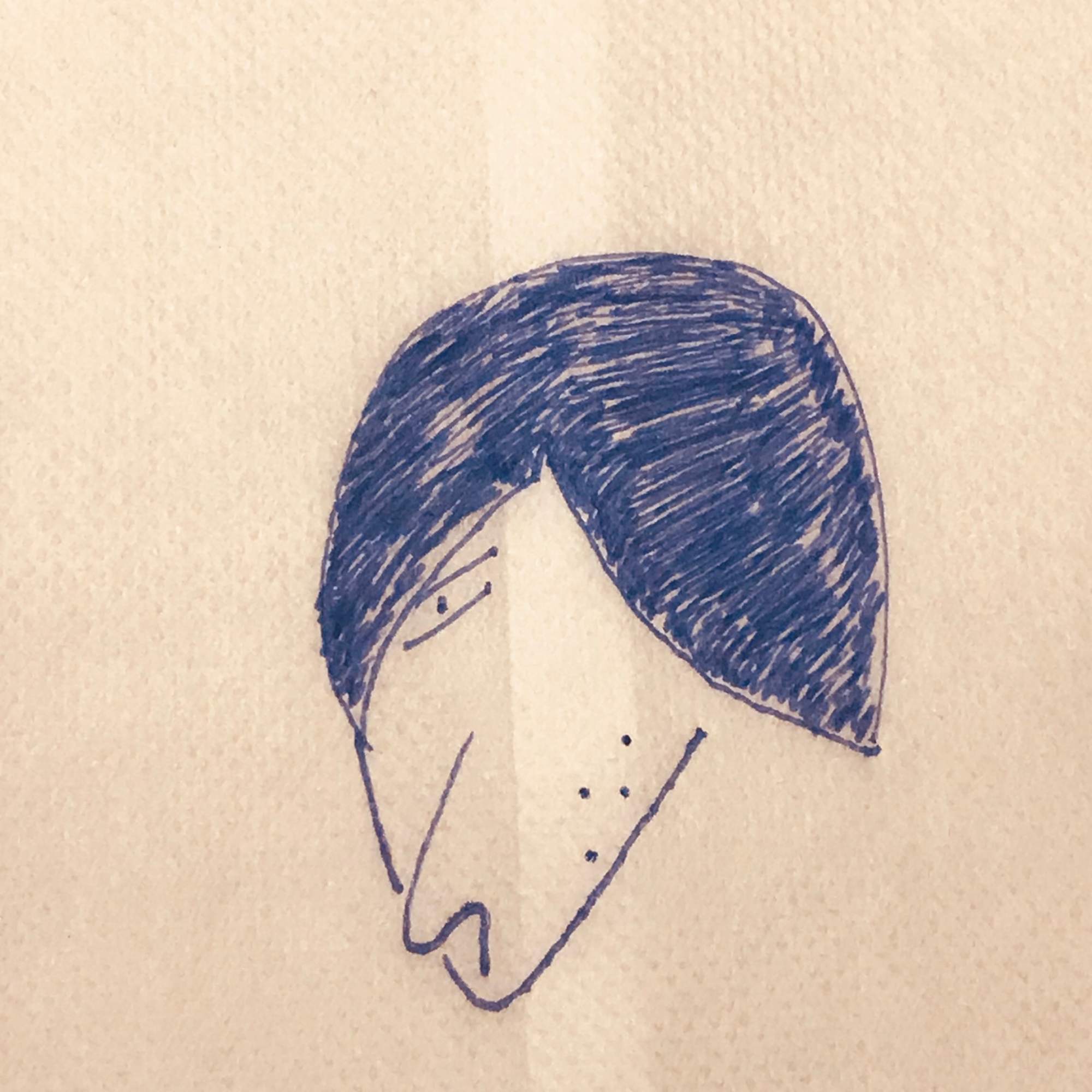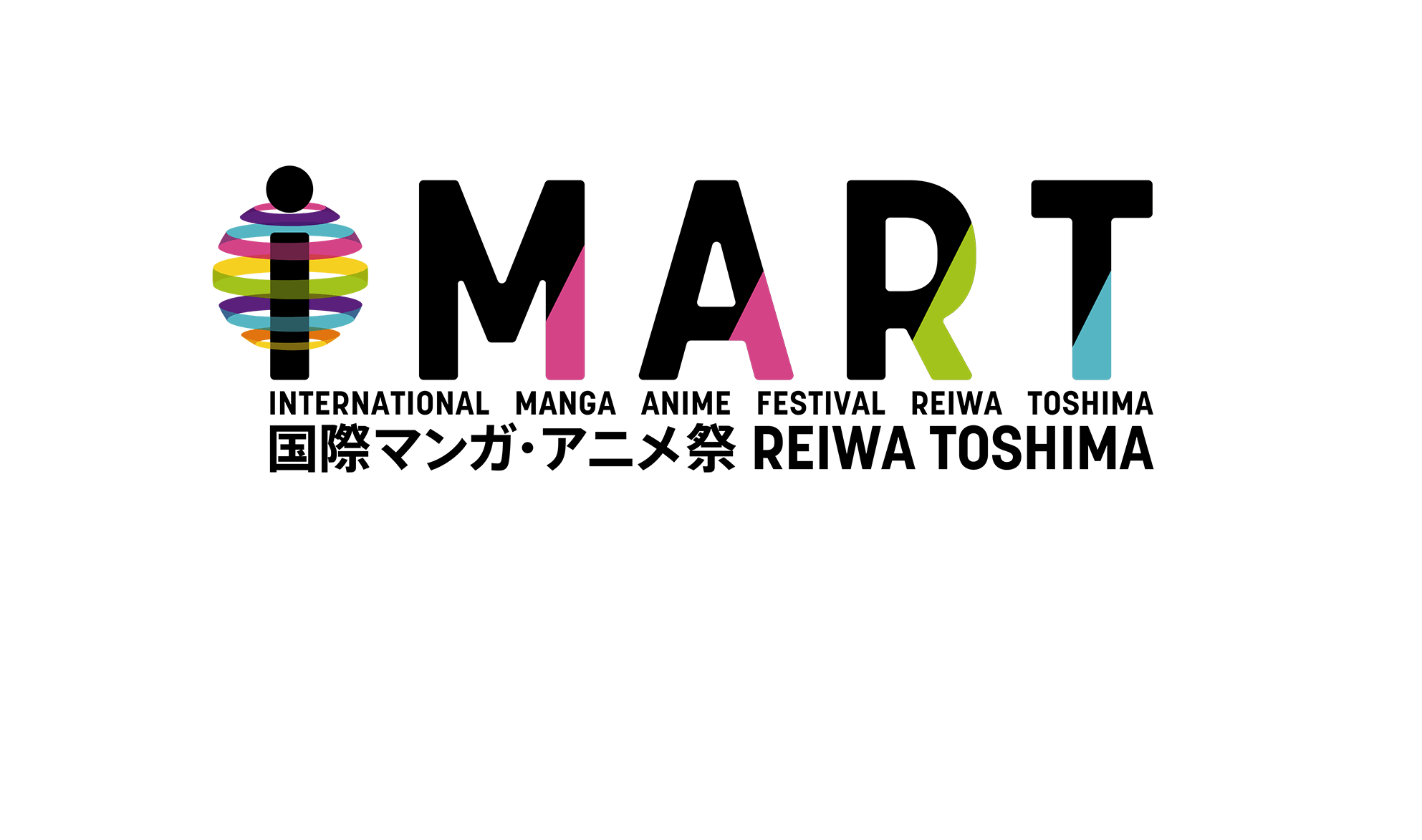
IMART2019年11月16日(土)
全セッションレポート(後編)IMART(第2日目・後編)
新たなマンガ家の姿 vol.1
ベテラン漫画家が開拓する新境地

- 登壇者
- 樹崎聖(マンガ家)
こしのりょう(マンガ家)
森田崇(マンガ家) - 司会
- 山内康裕
レポート(セッション概要)


セッション「新たなマンガ家の姿 vol.1 ベテラン漫画家が開拓する新境地」では、マンガ家に多彩な役割が求められている現在において、描くこと以外の新たな道を開拓したベテラン勢をゲストに迎えた。
樹崎氏は動きを加えたマンガをスクリーンに映し、役者が生でセリフを披露する公演「DomixモーションコミックLive」を紹介。こしの氏はコミュニティに参加して、マンガ教室や読書会、ライブペインティングなどを開催し、様々な業種と関わり合いを持つ中で活動範囲を広げていったと振り返る。森田氏はフランスの小説「アルセーヌ・ルパン」を原作とした『怪盗ルパン伝 アバンチュリエ』の版権を自ら管理し、原作小説とコラボレーションをしたり、物語の舞台であるフランスへの聖地巡礼ツアーを企画したりと、幅広い試みを展開中だという。
ディスカッションでは「これからのマンガ家は自分でプロモーションをしていく時代」という発言があった一方で、すべてを一人で行う困難さから「出版社の偉大さがわかった」との声も。3氏の取り組みの根源には「ずっとマンガを描きたい」という同じ気持ちがあり、その目標に向けて今後も可能性を探っていきたいと意気込みを見せた。
映画祭はいかに活用しうるのか?
アヌシーの事例から

- 登壇者
- 土居伸彰(新千歳空港国際アニメーション映画祭 フェスティバル・ディレクター)
山口晶(サンブリッジ取締役代表 CITIA* 日本代表・Rep) - 司会
- 数土直志
レポート(セッション概要)

左から、土居伸彰氏、山口晶氏、数土直志氏
最大規模のアニメーション映画祭であるアヌシー国際アニメーション映画祭は、世界最大のアニメーション見本市であるMIFAを併設する、アニメーションビジネスの拠点という側面を持つ。セッション「映画祭はいかに活用しうるのか? アヌシーの事例から」では、日本ではあまり知られていない、商談の場としてのアニメーション映画祭の機能と、その実践的な活用方法が、関係者の証言から明かされた。
まずは山口氏と土居氏がそれぞれ、各自が携わる映画祭についてプレゼンテーション。長い伝統と世界最大の開催規模を誇るアヌシーと、新興かつ小規模ながらその独自性が世界的に注目を集める新千歳空港国際アニメーション映画祭の比較がなされた。
世界のアニメーションを一望する網羅性が特徴のアヌシーに対して、アニメーションの概念を揺さぶる先鋭性が特徴の新千歳。スケールの異なる二つの映画祭の比較を通じて、映画祭ごとの異なるコンセプトが浮き彫りとなった。

後半ではMIFAの事例から、映画祭を活用して制作資金を得る実践的な方法がディスカッションされた。山口氏は、企画のコンセプトを言語化して説明する能力が不可欠と強調。日本人作家はその部分が苦手な傾向にあるのではないかとの見解を示した。
土居氏は、プロデューサーとしてMIFAのピッチに参加した経験から「映画祭は完成した作品を観る場所にとどまらず、作品が作られていく場所でもある」と述べ、映画祭が優れた作品を生みだすための土壌になると説いた。