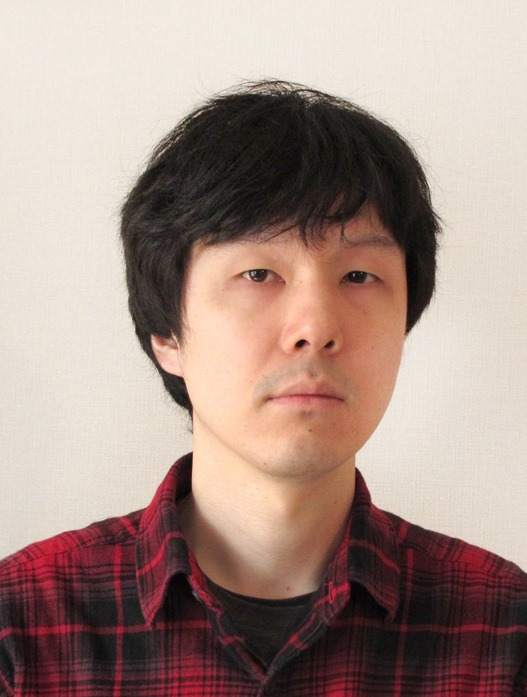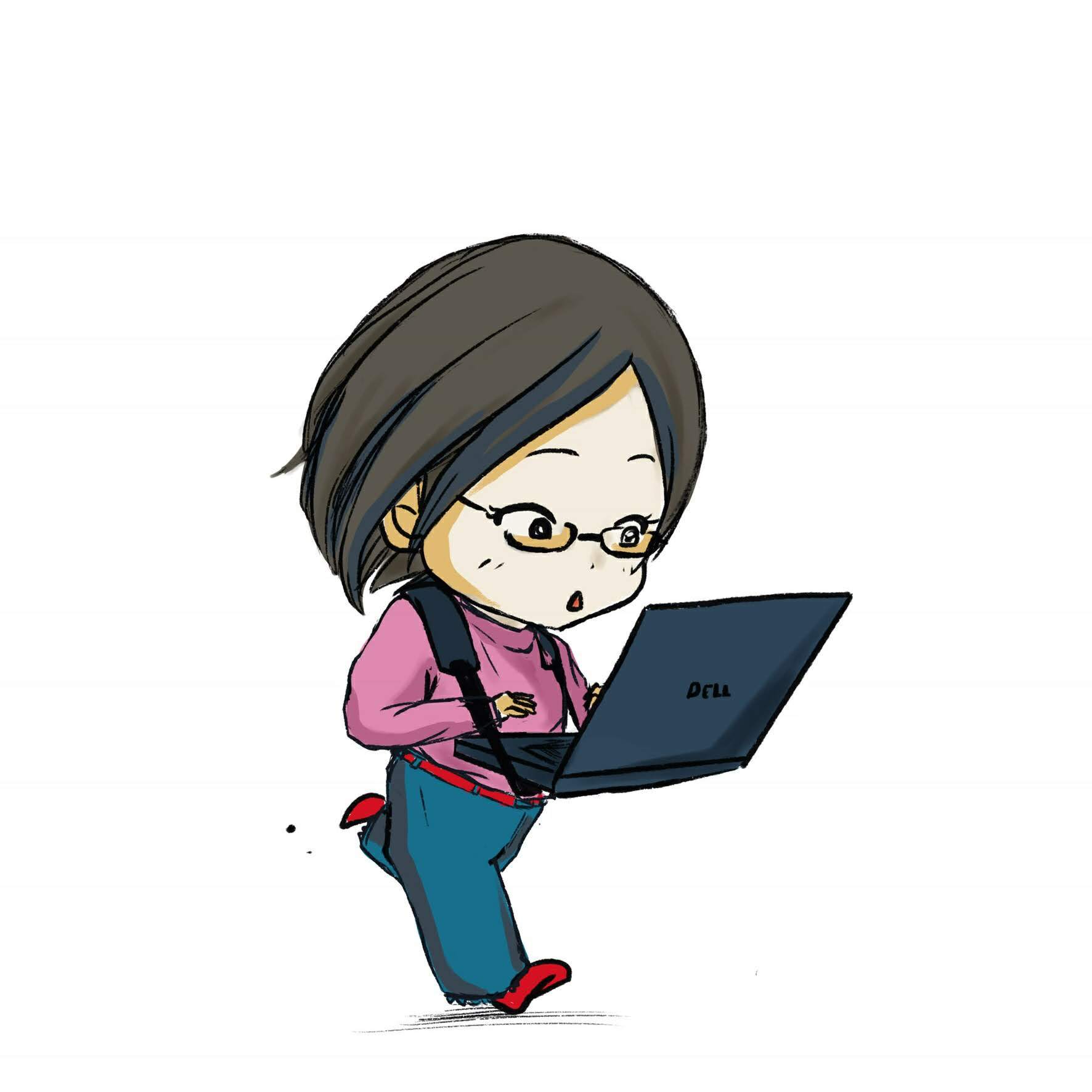拡大する「2.5次元」の世界いわもとたかこ
広がる担い手――演劇市場との境目小さく
舞台の中身そのものも日々変化している。そもそも演劇、特に小劇場の舞台では、限られた舞台空間に幅広いジャンルの作品世界を再現するためにいろいろな演出の知恵を絞ってきた。役者と演出、舞台装置に加え、観客の想像力に支えられながら、「完成」していくエンターテインメントで、観客をその世界に引き込むために、何が必要で何が不要かを考え抜いて作り上げられている。その手法は2.5次元舞台にも引き継がれ、『テニミュ』では、実物のテニスボールが登場しない代わりに、ラケットとボールの音、光をフックにそこには存在しない高速で動くテニスボールを想像させた。
この演出方法についてもそれまで小劇場を中心に様々な舞台表現を追求してきた演出家が2.5次元舞台の制作に関わり始め、幅が広がっている。
例えば劇団「惑星ピスタチオ」の演出家で劇作家の西田シャトナー氏は、高校の自転車競技部を舞台にしたマンガ『弱虫ペダル』の舞台化を手掛けた。劇場内に飾られた競技用自転車で観客の想像を膨らましながら、自転車のハンドルと役者の足の動きで激しい自転車競技の表現に挑戦した。それ以外にも、舞台装置を動かし演技をサポートする役者「パズルライダー」を取り入れた。
西田氏はインタビューなどで「『手で作る演劇』が自分の仕事だと思っている」と語っており、『弱虫ペダル』の舞台では舞台装置はパズルライダーと、ときには役者が協力して移動させる。こうした手作り感へのこだわりが、機械の力を借りず選手の筋肉と自転車でレースを乗り切る自転車競技にマッチしたとみられる。西田氏はこのことを2012年に弱虫ペダルの舞台についてTwitterで「舞台化は実写化ではない。いわば実体化だ!」と投稿している。
このほかにも劇団「柿喰う客」代表の中屋敷法仁氏や、演出家のウォーリー木下氏といった人々が2.5次元舞台の作品に関わり始めた。作曲家や振付師を含め、彼らが幅広い演出方法を持ち込んだことで、2次元の世界の舞台上での見せ方は変わりつつある。『ハイパープロジェクション演劇 ハイキュー!!』シリーズでは、プロジェクションマッピングやスクリーンへのコマの投影といったメディアートの技術も導入され、作品への没入感を強めた。『ハイキュー!!』では、作曲家の和田俊輔氏が舞台上での生演奏にも挑戦。『ミュージカル さよならソルシエ』では、音楽は舞台上のピアノで奏でられた。
もう一つの変化は、舞台上に乗るのが男性キャラクターだけではなくなったことだ。演劇プロデューサーの松田氏は前出の『AERA』のインタビューで「当時は男の子だけが出ている舞台はほとんどなかった。宝塚の逆パターンみたいな、男の子だけの美しい舞台ができたら成功するだろうとは思っていました」と語っている。その通りに『テニミュ』や『弱虫ペダル』の舞台には男性俳優しか舞台上には表れない。しかし、『ハイキュー!!』の舞台では、原作で重要な役割を持つ女性キャラも当たり前のように登場し、原作世界の熱を生み出すことに貢献している。
「体験重視」の流れ、3次元への接近を後押し
こうした市場拡大を後押ししたのは、ちょうどエンターテイメント全体でライブやコンサートといった体験を重視する流れが広がっていたことだ。音楽市場ではファンの楽しみ方がCDなどメディアで音楽を聴くだけでなく、ライブやフェスといったイベントに参加することが中心になりつつある。映画では映画館で上映中に声を出したりペンライトを振ったりできる「応援上映」が人気になってきた。アニメでも、キャラクターを担当した声優が生アフレコをするイベントなど、2次元の世界をより3次元に近づけようとする手法が人気になっていた。その中で、3次元の人間が2次元のキャラクターを演じる舞台は、究極の2次元から3次元へのアプローチといえる。
もちろんマンガやアニメには2次元でしか表現できないものや2次元だからこそ楽しめる演出や見せ方がある。一方で役者や演出家といった生身の人間が2次元の世界を3次元で表現しようとする過程では、もともとの作品やキャラクターの魅力に役者や演出家らの熱意や思い入れが加わる。その熱意や思い入れがもともとの原作が訴えたい本質とずれないことが大前提ではあるが、うまくはまれば観客を作品世界に引き込み、その心を震わせることになる。
これは役者や演出家が、舞台上でマンガやアニメ、ゲームではクローズアップなどを使うことで描かれない部分を演技や演出で埋めようとするときに、2次元の作品の持つイメージがより強まるからだ。舞台というエンターテインメントでは、マンガやアニメほど見ている人の視線をコントロールすることはできない。そのため、役者らは「そのキャラクターらしさ」を維持しながら、アニメやマンガでは省略される部分を観客に見せる必要がある。テニミュでいえば試合をしている選手以外のキャラクターの動きがそのひとつ。「そのキャラクターなら、その場面でこういう動きや発言をする」という役者や演出家の解釈と努力が積み重なり、キャラのイメージが膨らんでいく。
もちろんマンガやアニメ、ゲームといった原案とそのファンがいる分、ファンが作品に投影する思いや、作品が本来伝えようとする内容を裏切ることはできない。原作がある以上、キャラクターの造形を含めて2次元の表現に似せていくことになる。しかし似せようとする中でも役者という生身の人間が持つ色や特徴を消すことはできない。特に役者が個性的なキャラクターを演じるとき、キャラクターの性格や考え方、行動などの特徴と役者の性格や考え方が一致していれば、役者の熱のこもった演技が上乗せされ、キャラクターの魅力が一段と引き立つ。これは作品全体にもいえることで、プロデューサーや演出家が作品の本質を理解したうえで、舞台上に凝縮して表現したとき、もともとの作品が伝えたかったメッセージは増幅される。
また、公演が長期化すると、アニメなどでオリジナルキャラクターが登場するのと同じように、原作にはいなかったキャラクターが登場することもある。『テニミュ』の公演を長く見ている人は、いくつかの中学校で原作では名前しかでてこない選手が出演していることに気が付いているだろう。
もちろんデメリットもある。生身の人間がいる3次元であるため、2次元のマンガやアニメ、ゲームでは表現できた動きや演出が制限されることもある。2019年のJapan Expoで映画『東京喰種トーキョーグール【S】』に関するトークショーに登壇したプロデューサーの永江智大氏は、マンガやアニメを実写映画にする難しさについて質問されたとき、「基本となるテーマは変えない。あとは映画でしかできないことをやりたい」と述べた。俳優の窪田正孝氏は同じトークショーで「原作で(キャラクターの)40~50%はかたちがきまっている。(キャラの)リアルさを失わないようにするのが難しい」と話した。同じ課題は、2.5次元舞台でもいえることだ。
そのため賛否両論もある。キャラクターを含めビジュアルつきの原作のイメージがある分、そのイメージからずれたり外れたりすることがあれば舞台を支えるコア層になりうる原作ファンから敬遠されてしまう。少なくとも原作を使っている以上、同じ「らしさ」(もしくは原作を上回る「原作らしさ」)を持つことが求められるのだ。