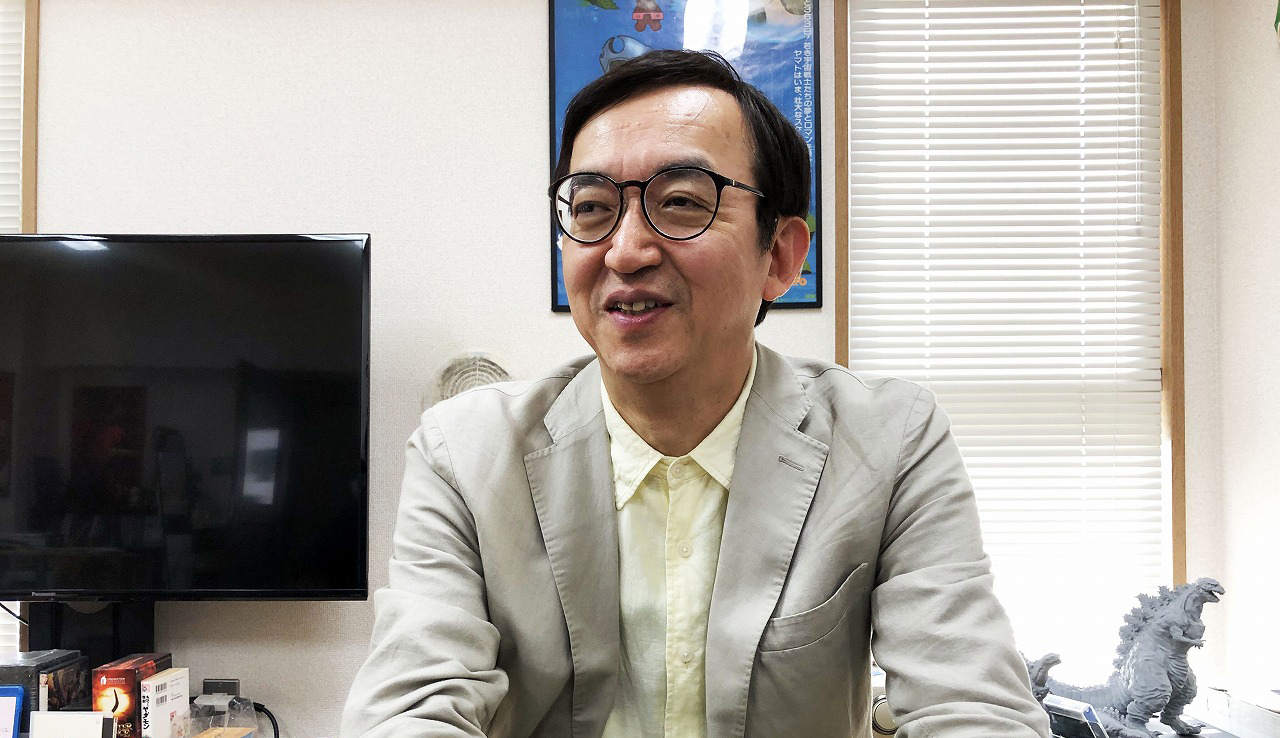
アニメはどう語られてきたのか(後編)
――氷川竜介が語る、人はなぜ感動するのか、
その感動の原点をいかにして残すのか氷川竜介インタビュー
日本アニメ史上における初の30分TVシリーズは言わずと知れた『鉄腕アトム』、1963年のことである。それに対して1958年生まれの氷川竜介氏はまさに、物心がつく前後からそれに触れ出した、TVアニメ第一世代のアニメ研究家だ。各種アニメ雑誌の登場以前、『月刊OUT』の『ヤマト』特集号(1977年)でライターデビューしたという経歴も、アニメライター第一世代と言えるものだろう。
今回、そんなTVアニメの発展と並走してきた氷川氏に、「アニメを語ること」をテーマにお話を聞いた。そのキャリアを順に追いながら、アニメを取り巻く社会的状況の変化やそのときどきの体験・課題をうかがうことを通じて、アニメをめぐる言説の歴史を浮き彫りにする。
前編・中編に続くこの後編では、『BSアニメ夜話』や明治大学大学院での講義など、近年の活動や展望を語ってもらった。
聞き手:高瀬康司、土居伸彰、構成:高瀬康司、高橋克則
フロンティアを歩いたあとが道になる
――2001年にはメーカーを退職し、文筆業専業として活動をスタートされます。それ以降で印象的な仕事は何でしょうか?
氷川 まずは『ラーゼフォン』(2002)ですね。メディアファクトリーさんがのちに「オフィシャルライター」と名づける仕事の先駆になりました。原作・総監督の出渕裕さんとは『ヤマト』のファンクラブ時代からの友人ということもあり、「誰も知らないオリジナル作品の情報をいかに劣化なく、総合的な観点で伝えるか」という言語化を氷川が一元化できないかという相談を放送前に受けました。その点で「評論のスタンス」に繋がっています。メインスタッフやキャストのインタビューから、あらすじやイントロダクション、アニメ雑誌の記事も含めて包括的に手がけ、現場にも通うことで、一つ作品に隅々まで深く関わり、「クリエイションの源泉」その最新形に迫った経験は大きかったです。企画の誕生から劇場版が完成するまでのオペレーション、エピソードがどのような発想から最終形に仕上がっていくのか、プロセスを深く知ることができましたし、CGと手描きのハイブリッドなどデジタル制作の可能性を含めて理解できてよかったです。
「オフィシャルライター」という仕事もそれ以前にはなかったはずで、「『OUT』にはライターという意識で参加したわけではない」と似ています。結局人生を通じて、枠があるから仕事を選ぶのではなく、そのときそのときで自分なりに最適な方法を探ってきた繰りかえしなのです。すべては、その結果でしかない。フロンティアを歩いたあとが道になる。後手に回りたくはないですね。
――また2004年からは『BSアニメ夜話』に出演し、「アニメマエストロ」などのコーナーを担当されます。
氷川 『アニメ夜話』はNHK BSの企画で、『BSマンガ夜話』の成功から論客を集めた評論番組を作ることがスタートで、アニメ技法について解説する特別コーナーに出演してほしいというオファーを請けて参加しました。「アニメマエストロ」とは氷川のことではなく、アニメを作る職人、名匠のことを指しています。第1回目の『銀河鉄道999』(1979)では、金田伊功さんのエフェクトアニメを取り上げました。以後は特殊効果や撮影効果といった技法をリストアップし、アニメを観るときの切り口には30種以上、様々なアプローチがあることを、映像ベースで提示できました。それぞれ「この作品なら自分はここにピークを感じている」という題材ですから、評論にもなっていると思います。
その後で大きかったのは、2010年から3年間、文化庁メディア芸術祭でアニメーション部門の審査委員を務めた経験です。樋口真嗣監督からのご推薦がきっかけでしたが、文化庁の仕事という点で、公共、歴史、国際性などパブリックな意識が強まりました。作品評価はもちろん、日本のポジショニングや、国家がメディア芸術をどう定義しているのか、複合的な要素を考慮して受賞作品を論議します。受賞歴も参考にしつつ、過去と現在と未来を繋ぐ、歴史的視点で評価を考えました。受賞作リストは、アニメを研究するうえで歴史の基礎情報の一つになりますから、広い視野を持って審査することを心がけました。
振り返ると、15年ほどかけて徐々に「アニメを語ること」とその「公共性」を強く意識するようになっていますね。それがATAC(特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構)でのアーカイブ事業をはじめとした、近年の活動を支える基盤になっています。


















