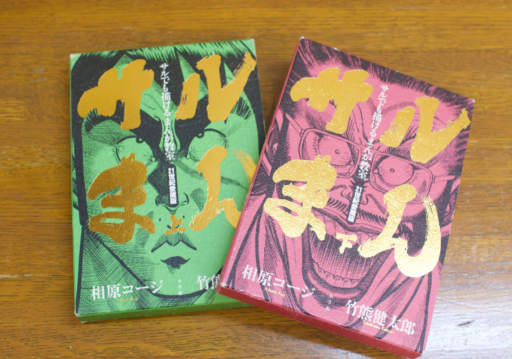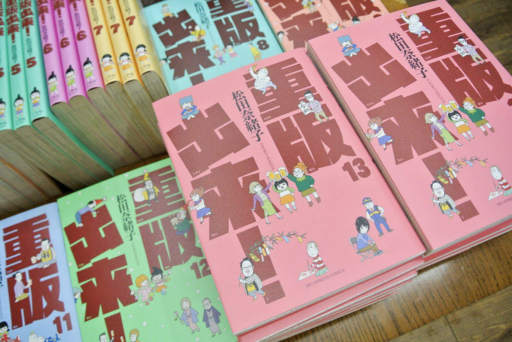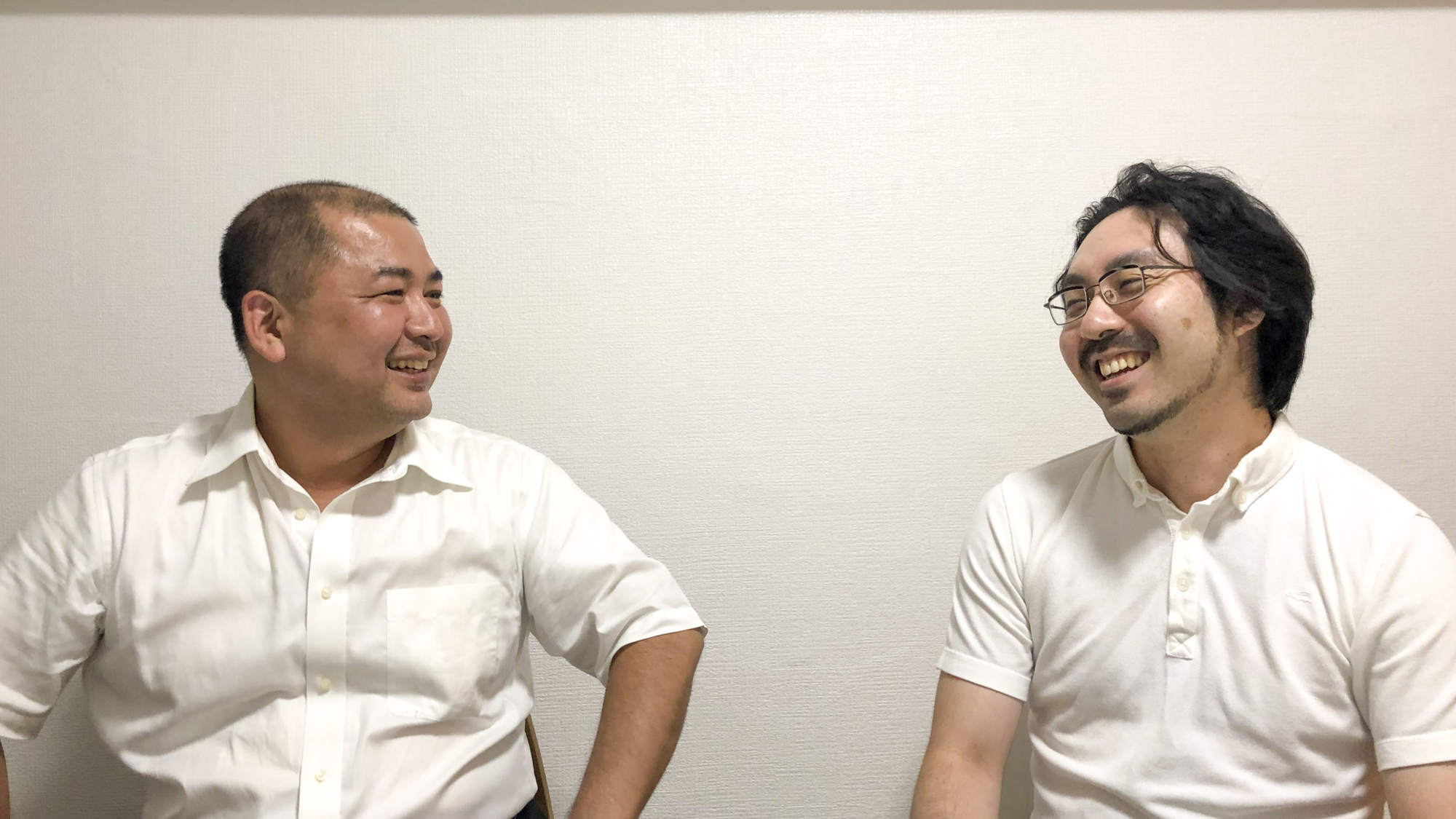
電子化の波とともに変革期を迎えた
2010年代漫画産業(後編)菊池健インタビュー
すべての動機は“支援欲”にある
――一般企業に勤めていながら、転職して漫画に関わる仕事に就かれたのはなぜなのでしょう?
菊池 きっかけは、中央アメリカのホンジュラスへ旅行をしたことです。ホンジュラスには数ヶ月間暮らしていたのですが、どうもアジア系の人間は珍しいらしく、散歩をしていると子どもたちにスペイン語で「中国人だ!」とよく言われたんですね(笑)。それで「僕は日本人だよ」と言い返すと、その子らは「ドラゴンボール!」と言いながら「かめはめ波」のポーズをするんです。「ナルト!」と叫んで、手裏剣を投げるジェスチャーをされたこともありましたね(笑)。そのときに、地球の裏側にある国の子どもですら、日本の漫画やアニメを知っているという事実に衝撃を受けたんです。
なぜ日本の作品に詳しいんだろうと気になって調べてみたところ、アメリカのロサンゼルスやマイアミなど南部の州はスペイン語をしゃべれる人が多くて、そこで流行ったものはメキシコに輸出されるという流れがあることがわかりました。つまりアメリカで人気になった『DRAGON BALL』や『NARUTO -ナルト-』が、メキシコの放送局でスペイン語に翻訳されて、それがスペイン語圏であるホンジュラスで観られていたと。さらにホンジュラスだけでなく、数億人いる中南米のスペイン語圏の国で放送されていました。
――すごい人数ですね。
菊池 にもかかわらず、ホンジュラスでは漫画やアニメのグッズがほぼ販売されていなかったので、誰も作品にお金を落とすことができないわけです。膨大な数のファンがいるのに、TV放映権関係くらいしかビジネスに繋げられていない。それを知ったとき、この状況を何とかできないだろうかと思ったんですよ。それが漫画に関わりたいと思った直接のきっかけです。
――そんな中、菊池さんは漫画家志望者を支えたり、面白い漫画を紹介するレビューを書いたりと、漫画に間接的に関わるような仕事を選ばれています。それはなぜなのでしょうか?
菊池 作品そのものよりも作家に興味があるからでしょうね。誤解を恐れずにいえば、私は振り切った人たちが好きなんですよ(笑)。だから特殊な能力を持っている人を、ビジネスへつなげるための仕事にばかり携わってきました。それは裏を返せば、私は自分自身が普通だということにコンプレックスがあるのかもしれません。だからこそ、不器用だけれども特殊な才能を持った人をサポートしたいという、非常に強い欲求がある。“支援欲”とでも言えばいいでしょうか。京まふでアニメの商品化に力を注いだのも、売れればクリエイターに還元されるという気持ちが強かったからですし、「マンガ新聞」のレビューもこれをきっかけに作品を買ってもらえればうれしいからです。私のモチベーションはそういう“支援欲”にあるんだと思います。

――では今後も、才能のある人が世に出ていく手助けを続けていきたい?
菊池 はい。そのままでは尖りすぎていて受け入れられがたいものを、社会の中へきちんと着地させるサポートができた瞬間に、最大の喜びを感じます。特別な才能を活かせるような場所を提供したり、作家本人が気付いていない長所を指摘したりして、それが結果へとつながっていくことがすごく楽しいんですよ。それが私の行動の一番の根っこですね。